今回は【三大栄養素】について書いていきます。
皆さんご存じ三大栄養素です。
学校でも習いますし、何かしら加工食品を買うときに
必ず目にするので、知らない方はいないと思います。
知っている人が多いので、もう少し深堀して書いていこうと思います。
三大栄養素とは、炭水化物、たんぱく質、脂質の3つになります。
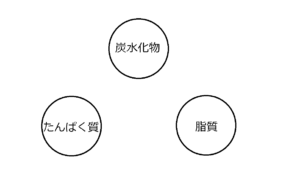
炭水化物
炭水化物=糖質+食物繊維
炭水化物は糖質と食物繊維からなります。
炭水化物の表記は糖質と食物繊維の合計です。
食物繊維はエネルギーにはなりませんので、基本的に炭水化物と称されるものは、
糖質を指しています。
炭水化物(糖質)は色々分類があり
・単糖類……ブドウ糖、果糖、ガラクトースなど
・二糖類……ショ糖、乳糖、麦芽糖など
・少糖類……オリゴ糖
・多糖類……でんぷん、グリコーゲン、ペクチン、グルコマンナン、アガロースなど
などがあります。
炭水化物は、主に主食とよばれる料理に使われる食材に多く含まれています。
炭水化物を含む食品は数多くあり、代表的なものを以下のような食品になります。
・炭水化物を多く含む食品
・食材米(ご飯、白飯、玄米、おにぎりなど)
・小麦粉(パン、うどん、そうめん、お好み焼き、たこ焼き、パンケーキなど)
・いも類(じゃがいも、さつまいもなど)
・そば
糖質は消化・分解されるとブドウ糖になり、腸から吸収されて肝臓に送られます。
血液と共に全身に行き渡り、1g当たり4kcalのエネルギー源として働きます。
体内における必要量は少なく、余ったブドウ糖はグリコーゲンとして筋肉や肝臓に貯蔵され、
必要に応じて再度エネルギー源として利用されます。
グリコーゲンは約400gしか保存しておくことができないので、
行き場のなくなったブドウ糖は脂肪組織に運ばれて体脂肪となります。
一日に食事から摂取するエネルギー(kcal)の
50~65%に相当する量を摂取することを厚生労働省は推奨しています。
男性・・・糖質300g以下、食物繊維20g以上
女性・・・糖質200g以下、食物繊維20g以上
だいたいこれくらいは取るようにした方が良いかと思います。
たんぱく質
たんぱく質には動物性と植物性の2つがあります。
動物性たんぱく質
動物性たんぱく質は主に動物から摂取でき、
魚介類を含む動物由来のたんぱく質のことを指します。
肉類、魚介類、卵、乳製品などに含まれています。
動物性たんぱく質の体内での吸収率は約97%です。
植物性たんぱく質
植物性たんぱく質は主に植物から摂取でき、
植物由来のタンパク質のことを指します。
米、小麦、大豆、種類によっては野菜や果物にも含まれているものがあります。
植物性タンパク質体内での吸収率は約84%です。
簡単に説明すると2つのたんぱく質はこのような感じです。
たんぱく質はアミノ酸からできています。
そして、アミノ酸はたくさんあるので、たんぱく質の種類も
この組み合わせによって無数にあります。
たくさんあるので、どれを取ればいいのかイマイチ分からない人もいると思います。
そんなときは、この組み合わせの中でBCAAと呼ばれるものを取りましょう。
BCAAとは、バリン、ロイシン、イソロイシンの3つのこと指します。
このBCAAは筋肉中のタンパク質を構成しているアミノ酸の中の占める割合は約35%と言われています。
BCAAはパフォーマンス向上などのために筋力トレーニングをする場合、
大切な栄養素の一つとなります。
そしてこの中のロイシンは筋肉の合成に強く影響を与えると考えられています。
〇ロイシン、イソロイシン、バリンの順に高い!?
| g/100g | ホエイ | カゼイン | 大豆たんぱく質 | 卵たんぱく質 |
| バリン | 5.9 | 5.9 | 5 | 6.4 |
| ロイシン | 12.2 | 8.9 | 8.2 | 8.4 |
| イソロイシン | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 5.7 |
| 合計 | 24.2 | 19.5 | 18.1 | 20.8 |
上の表はたんぱく質100g当たりのBCAA含有量です。
筋肉にロイシンが一番影響を与えると考えられている理由がこれになります。
3つのうちロイシンが多いのは分かりますね。
加えて筋肉を作る上でプロテインを取る人がいると思いますが、
それによく含まれているホエイはロイシンが50%もあります
| 食品名 | バリン | ロイシン | イソロイシン | 合計(mg) |
| まぐろの赤身 80g | 1040 | 1600 | 960 | 3600 |
| あじ 中一尾 90g | 864 | 1350 | 775 | 2989 |
| 鶏むね肉 80g | 784 | 1280 | 728 | 2792 |
| 高野豆腐 16g | 432 | 720 | 416 | 1568 |
| 牛乳 200g | 400 | 640 | 340 | 1380 |
| たまご 1個 50g | 380 | 500 | 305 | 1185 |
| 納豆 40g | 332 | 520 | 304 | 1156 |
| チーズ 20g | 380 | 460 | 240 | 1080 |
上の表はBCAAが多く含まれる食品になります。
このように食品に含まれるBCAAの中でもロイシンが多いことが分かります。
たんぱく質は筋トレをしている人には必須の栄養です。
もし何を取ればいいのか迷ったときはBCAA取るようにしてみましょう。
なお、食事でたんぱく質を取る場合は動物性、植物性などバランスよく摂るようにしましょう。
脂質
脂質は肉の脂や植物油、コレステロールなどの主な成分です。
脂質は大きく分けると、
「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」
の2つにあります。
飽和脂肪酸は常温で固まる性質があります。摂り過ぎると中性脂肪やコレステロールが増え、
高脂血症や動脈硬化が進むおそれがあると言われています。
不飽和脂肪酸は常温で固まりにくい性質があります。
血中の中性脂肪やコレステロール値を調節する働きがあると言われています。
例えば、どんなものにどういうものが含まれているのかは↓の表になります。
| 種類 | 主な脂肪酸 | 食品 | |
| 単価不飽和脂肪酸 | オレイン酸 | ひまわり油、サフラワー油、オリーブオイル、マカダミアナッツ、ヘーゼルナッツなど | |
| 多価不飽和脂肪酸 | n-3系 不飽和脂肪酸(必須脂肪酸) | αリノレン酸 | シソ油、ごま油、菜種油、アマニ油、くるみなど |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | あんこうのきも、くじら、まぐろの脂身、さば、うなぎなど | ||
| エイコサペンタエン酸(EPA) | あんこうのきも、くじら、さば、うなぎ、さけなど | ||
| n-6系 不飽和脂肪酸(必須脂肪酸) | リノール酸 | サフラワー油、ひまわり油、綿実油、大豆油、コーン油など | |
| γリノレン酸 | 月見草の油や種子、母乳、からすみ、くじら、にしんなど | ||
| アラキドン酸(ARA) | ぶたレバー、卵黄、からすみ、さわらなど | ||
脂質は、身体の主要なエネルギー源になるほか、細胞膜やホルモン、
体の仕組みに働きかける生理活性物質の材料になるといった重要な役割があります。
余った脂質は中性脂肪として主に脂肪細胞に貯蔵されます。
不足すると、疲労しやすくなったり免疫力が低下したりするため、
適度な脂質は身体にとって非常に大切です。
しかし現在、食生活の欧米化により日本人の脂質摂取量は増え、
むしろ摂りすぎによる肥満や脂質異常症、メタボリックシンドローム、
動脈硬化などといった生活習慣病が問題となっています。
働きエネルギーを産生する食べ物に含まれる脂質は体内で分解され、
細胞の中で1gあたり9kcalのエネルギーを産生します。
エネルギーは炭水化物やたんぱく質からも作られますが、
これらのエネルギー産生量が1g当たり4kcalということと比べると、
脂質はエネルギー効率が高い栄養素といえます。
燃料として貯蔵される使い切れなかった脂質は他のエネルギー源同様、
中性脂肪に変えられ、体脂肪として蓄えられます。
そのため脂質をとりすぎると肥満や脂肪肝の原因となり、
さらに血液中の中性脂肪やコレステロールが増える脂質異常症や、
メタボリックシンドローム、動脈硬化、心筋梗塞や脳梗塞などの原因にもなります。
身体を作る成分となる脂質は細胞膜の構成成分になります。脂質は水を弾くため、
細胞の内外に必要以上に水が出入りしないよう作用します。
脂質はそのほかホルモンや生理活性物質といった、体の仕組みに働きかける物質の材料にもなっています。
このように細胞レベルでも重要な働きをするので、
ダイエットだからといって極端に脂質を制限するのは厳禁です。
脂溶性ビタミンの吸収をよくするビタミンの中には、
水には溶けず油脂に溶けるものがあります。
脂質はこれらのビタミンを溶かし込んで、吸収しやすくします。
脂質が不足すると疲労、やせ、肌荒れ、体力低下、免疫能低下、月経異常などなりやすく、
脂質を摂りすぎると肥満、脂肪肝、脂質異常症、動脈硬化などになりやすくなるため気を付けましょう。



